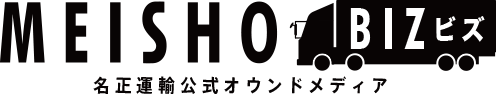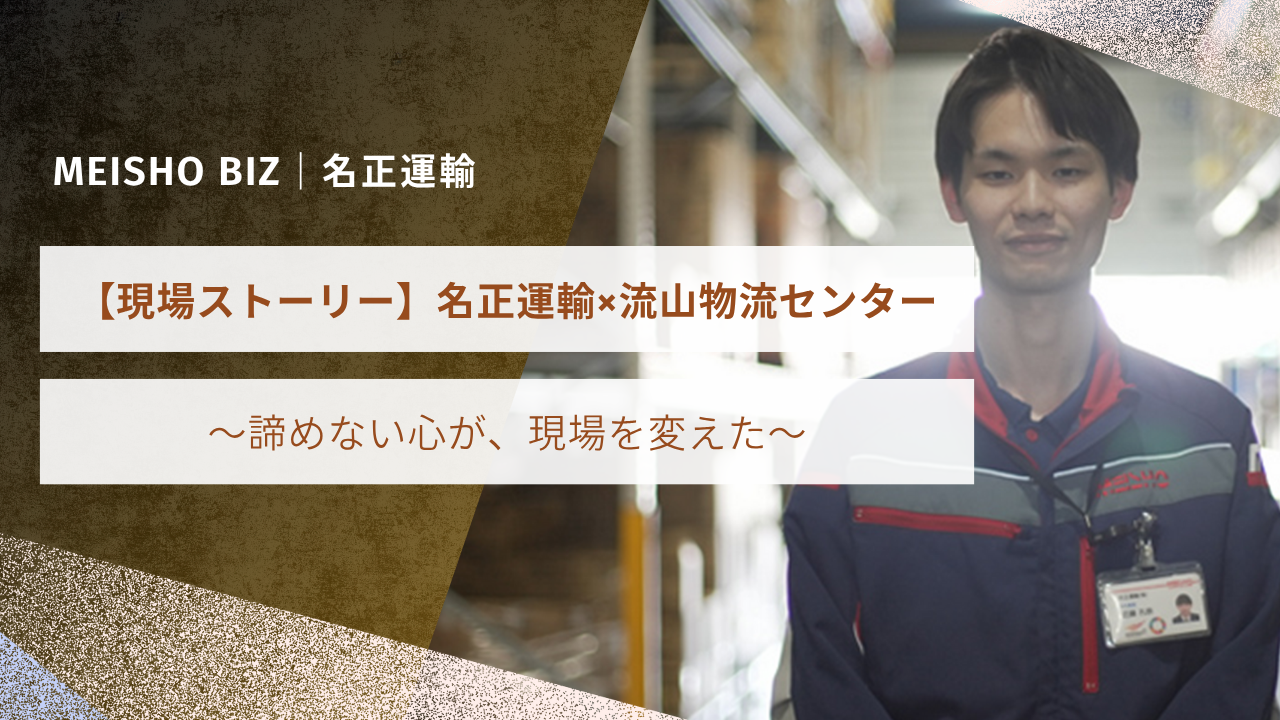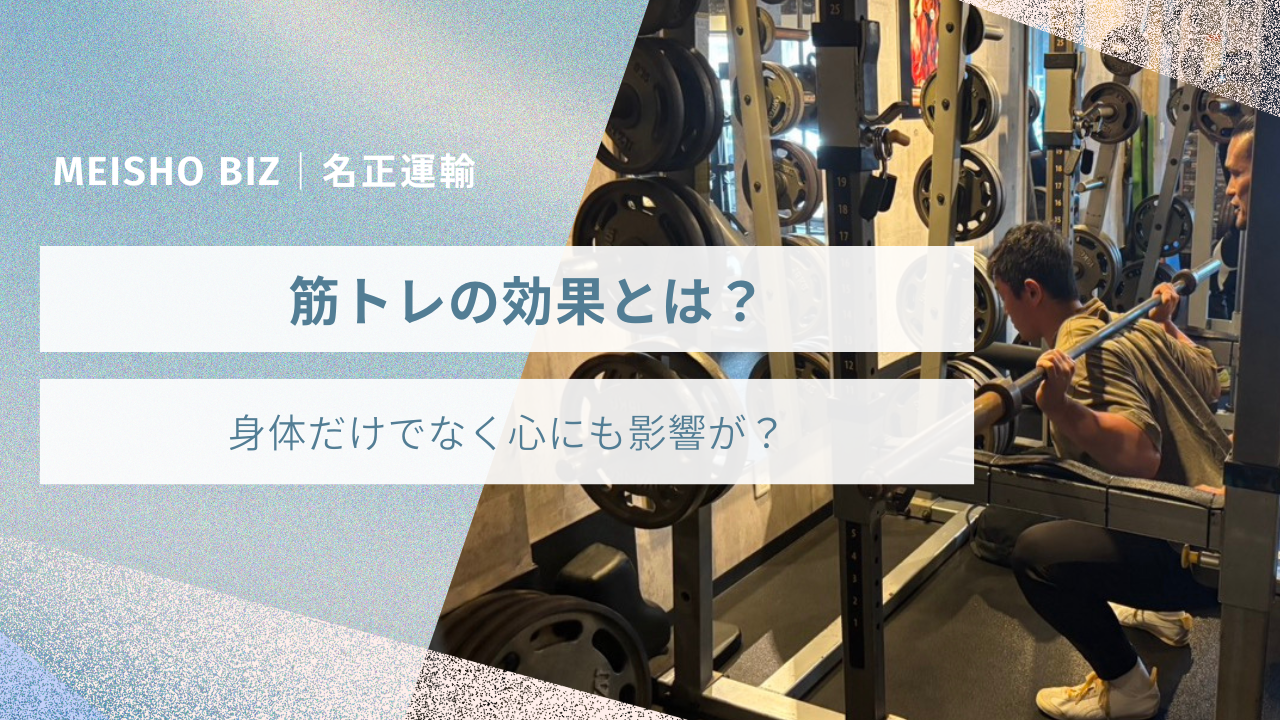- トップ
- 相次ぐ対面道路での事故
相次ぐ対面道路での事故~対面道路の危険性と注意点~
2025.11.07
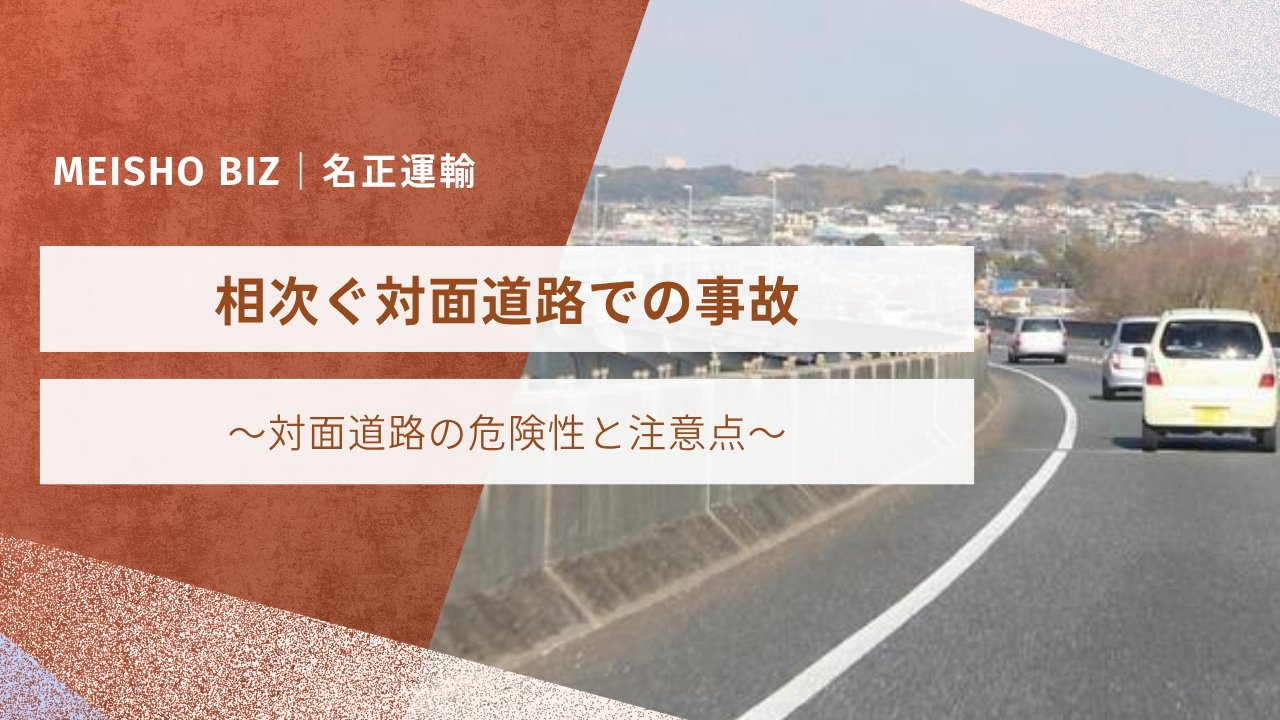
ここ数年、全国で「対面通行の道路」で発生する交通事故が増加しています。
センターラインのない生活道路や、郊外の産業道路などでの正面衝突事故・接触事故は、日常の移動や配送業務の中でも頻発しており、物流業界においても重大なリスク要因となっています。対面道路での安全運転は社会全体にとっても非常に重要なテーマです。
本記事では、対面道路が抱える構造的な危険性と、安全運転のための注意点について解説します。
対面道路とは?構造的な危険性を知る
「対面道路」とは、上下線が同じ車線を共有する道路のことを指します。
多くの場合、"中央中央分離帯がなく対向車線と車道が分かれていない状態"や、"センターラインがなく片側一車線の幅も十分でない状態"のため、対向車との距離を誤ると衝突リスクが高まります。
特に以下のような環境では、危険性が増します。
・センターラインがない道路
→ 境界の判断が曖昧になり、車線の「はみ出し」に気づきにくい。
・道幅が狭い生活道路・農道・工業団地内の通り
→ 対向車や歩行者、自転車と同時に通行できないケースが多い。
・カーブや勾配が多い道路
→ 見通しが悪く、対向車や障害物を発見するのが遅れる。
・夜間・雨天・霧など視界不良の状況
→ 路肩やセンター位置が見えづらく、車両位置がズレやすい。
物流車両は大型・中型トラックが多く、車幅が広い分、わずかなズレでも大きな接触事故につながることがあります。

対面道路 例(1)

対面道路 例(2)
事故が発生しやすいシーン
実際の事故原因を振り返ると、「一瞬の油断」が悲劇を生むケースが少なくありません。
以下は、対面通行道路で起こりやすい典型的な場面です。
・カーブのすれ違いでの正面衝突
→ 内側を走りすぎてセンターを越える/対向車も外側に膨らむ。
・交差点や路地からの飛び出し
→ 住宅地では自転車・歩行者の飛び出しも多く、ブラインド交差点で接触。
・スマートフォンやナビ操作中のわき見
→ 数秒の注意散漫でセンターを越え、正面衝突に至る。
・夜間走行中の視認ミス
→ 対向車のライトが眩しく、無意識に左寄り・右寄りに偏る。
安全運転の基本は「自分が注意すれば防げる」という意識です。特に対面通行道路では、状況に応じた「先読み運転」が不可欠です。

企業としての安全への取り組み
当社では、3PL(Third Party Logistics)企業として、荷主企業様からお預かりした貨物を安全かつ確実にお届けするために、日々安全管理体制を強化しています。
主な取り組みは以下の通りです。
■デジタルタコグラフによる運転行動の分析
車速・車間距離などを自動検知し、教育データとして共有。
また、ドライブレコーダーでの社内ルールチェックを定期的に行う。
■定期的な安全ミーティング・ヒヤリハット共有会
現場での実例をもとに、具体的な回避行動を全員で学習。
■運行ルートの事前確認と改善提案
配送ルートごとの道路状況を現場社員が確認し、
危険箇所はルート再設定や通行時間調整を行う。
物流業は「時間」と「安全」のバランスが常に求められる業界でもあり、社会を支えるインフラであると同時に「道路を使う責任」を伴います。
当社では「安全を最優先にした運行管理」を徹底しており、高い安全意識と品質を保ち続けています。
まとめ~日常の道路にこそ最大の危険がある~
事故は高速道路よりも、身近な生活道路・対面通行の道路で発生する割合が高いことが警察庁の統計でも示されています。
――毎日の慣れた道ほど、油断が生まれやすい――その油断こそが、最も危険です。
ドライバー一人ひとりが「自分は被害者にも加害者にもならない」という意識を持ち、
安全確認を怠らず、譲り合いの心で運転することが、事故ゼロへの第一歩です。
当社は、3PL企業として物流を通じて社会を支えるとともに、交通安全の輪を広げる活動にも引き続き取り組んでまいります。